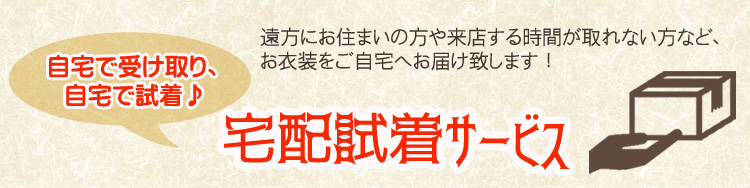2025.04.08 | 婚礼衣装について
打掛・引振袖の歴史

ご来店くださったお客様からご質問いただく事で、
「打掛ってなんですか?」と。
その形だったり意味みたいなものは何か?を疑問に思われるそうで。
私自身も、昔は身分の高い女性しか使用できなかったが町娘の憧れであった白無垢が時代とともに皆に浸透していった…(※所説あり。)とか布団だった…(※所説あり。)など曖昧な事しかお伝え出来ていなかったので調べてみました。
昔のことなので所説あり。については否定でできませんがそうだったのでは?と思う内容になっています。
打掛の歴史は室町時代まで遡り、武家の女性が正装として着用していた着物に起源があります。
時代とともにデザインや色彩が変化し、江戸時代には正式な婚礼衣装として認識されるようになりました。
・室町時代に裕福な武家の女性が小袖の上に羽織って着用していたのが発祥
・武家の女性が下に着ていた着物で、身分や格式を示す役割を果たしていました。
・白打掛(白無垢)が普及していました。
▼
・武士の装いが派手になり始めたため、より豪華な色打掛も生み出されました。
▼
・江戸時代になると、大奥などの高位女性や、上級女官にも広まった。
・江戸吉原などの遊郭の上級女性の正装でもあった。
・特に赤や白といった色が主流となり、結婚式や特別な儀式での着用が増えてきました。
【庶民の打掛の着用】
・社会が安定し、経済力が向上したことで、庶民の間でも打掛を着用する文化が広がりました。
・特に富裕な商家の結婚式では、花嫁が白無垢から色打掛へと衣装を変える習慣が生まれました。
・打掛のデザインや色彩が豊かになり、町娘など多くの女性が礼服として着用するようになりました。
・色打掛は、その名の通り色鮮やかなものが多く、花嫁の幸せと豊かな生活を象徴する衣装として、多くの人々に愛されてきました。
▼
・西洋文化の影響を受け、打掛のデザインや着用のスタイルも変化していきました。
・色鮮やかな模様や刺繍が特徴で、絢爛豪華な雰囲気を持つ。
・裾の袘には厚く綿が入っており、化学染料で鮮やかな赤に染められている。
・旧家の女性が着用したものには、刺繍で吉祥文様などを表した豪奢な打掛が見られる。
・明治に入ると、白無垢を着る風習が廃れ、色直しに用いた黒紋付裾模様が婚礼の衣装となりました。
▼
・婚礼が再び豪華になると貸衣裳が主流となり、神前結婚式では白無垢、披露宴では色打掛が主流となりました。
・現代では、正装として和装の結婚式の衣装に選ばれています。
・日本でウェディングドレスが普及し始めたのは1873年の長崎からでした。
・全国的に大流行したきっかけとしては、現在の上皇后陛下である美智子様がご成婚パレードで着用された婚礼衣装でした。
この様な流れになって行ったそうです。
では【白無垢】・【色打掛】・【引振袖】をもう少し詳しく見ていきましょう。

・平安時代には、白は高貴な色とされ、貴族の女性が神前での儀式や重要な行事の際に白い衣装を身に着けていました。
・室町時代には幕府によって礼道教育が進められ、結婚の方式が細かく決められました。
・室町時代から江戸時代にかけて、白無垢は花嫁衣裳、出産、葬礼、経帷子(きょうかたびら)、切腹の際の衣服とされました。
・明治時代に洋式慣行が入って以降、葬礼等に用いる衣服が黒とされるようになり、白無垢は結婚式(神前挙式)で花嫁が着用する婚礼衣装と式服の下着に残るのみとなりました。
・白無垢は神聖な色としての認識があるため多くの花嫁に選ばれています。
・白無垢を着るということは、「新婦の身の清浄を表し、けがれのない姿で神に誓う」ことでもありました。
・白無垢は新郎新婦が一体となって新しい家庭を築く意志の表れとしても考えられてきました。
現代では、白無垢と同様に新婦が着用する正礼装の一つです。

・室町時代中期:武家の女性が下に着ていた着物で、白打掛よりも格下の着物とされていました
・江戸時代:裕福な町娘の間で華やかな色打掛が主流となり、礼服として認識されるようになりました
・明治時代以降:西洋文化の影響を受け、デザインや着用のスタイルが変化していきました
・現代:白無垢と同様に新婦が着用する正礼装の一つとして、花嫁衣装として馴染みがあります
・鶴亀や鳳凰など伝統的な絵柄が描かれているのが特徴です
・お祝いの色である赤以外に様々な色があります
・色打掛から白無垢には戻れないという着用のルールがあります
・色打掛は、日本の豊かな文化と歴史を映し出す鏡のような存在です。時代ごとの美意識や価値観、さらには着る人の願いや個性を映し出しています。

・平安時代には宮廷の女性たちが長い裾を引きずる衣装を着用していた。
・江戸時代後期には、黒地の引き振袖が武家の上流階級の花嫁衣装として用いられていた。
・昭和初期に一般的な婚礼衣装として取り入れられるようになった。
・戦後の高度経済成長期にぜいたく思考が高まり、一度は絶滅しかけたが、近年その魅力が再評価されている。
・通常の振袖よりも裾が長く、地面に触れるほどの長さがある。
・裾を引く所作には「この人についていきます」という意味が込められている。
・裾の長さがその人の社会的地位を象徴するものとされていた。
和装の婚礼衣装ですが、意味や歴史を知るとまた違った魅力が涌いてきます♪
とは言え、そんなことは気にせず直観や好きな柄行やお色で選んでくださいね♡
●華結びの衣装レンタルは全国どこへでも往復送料無料でお届け致します。
来店のご予約・衣装に関するお問い合わせはこちらから
遠方にお住まいの方、時間が取れずご来店が難しいお客様には【宅配試着サービス】もございますのでぜひご活用ください。
※宅配試着サービスの詳細はこちらから